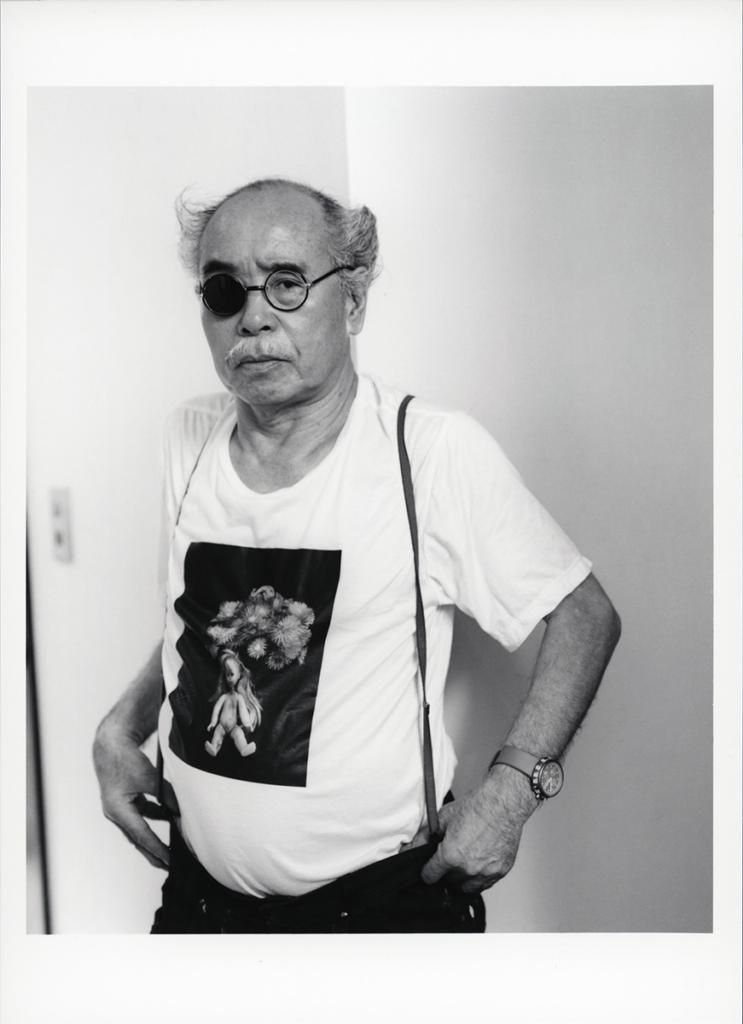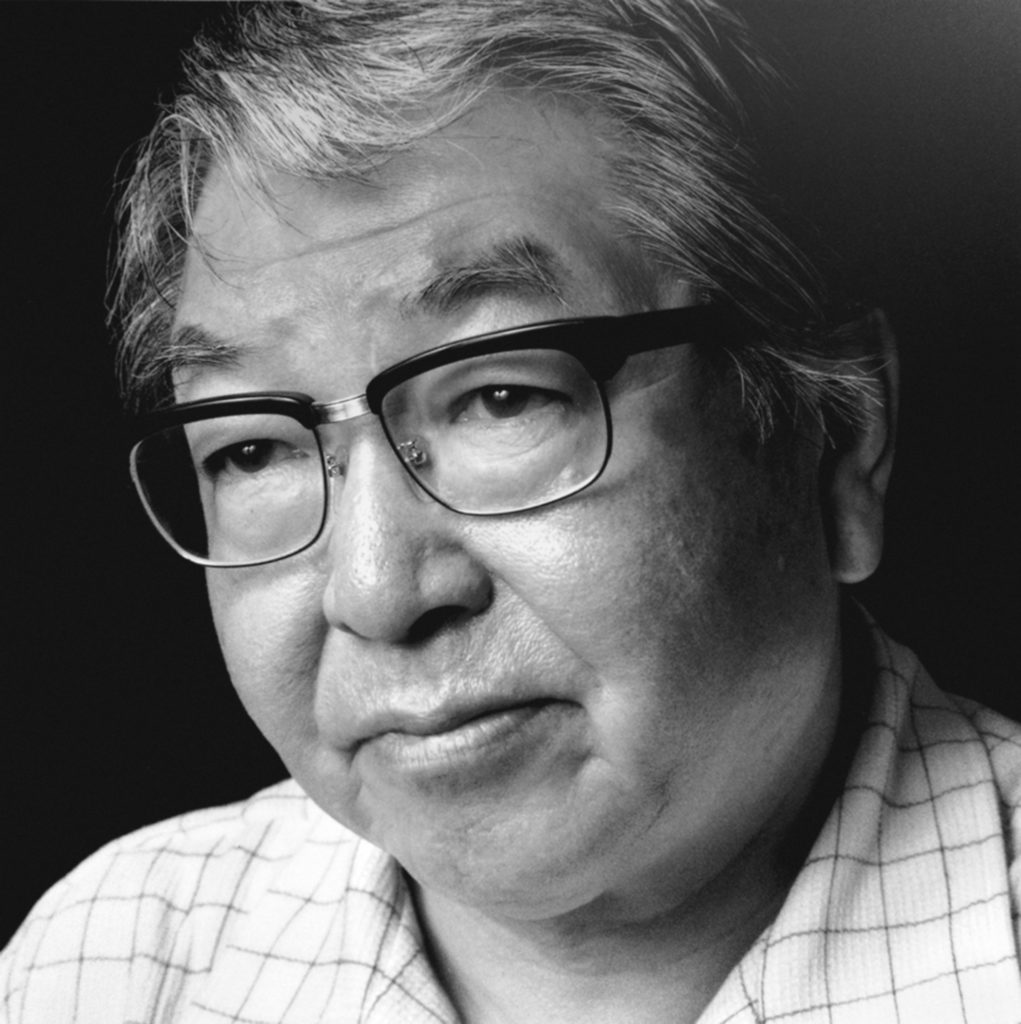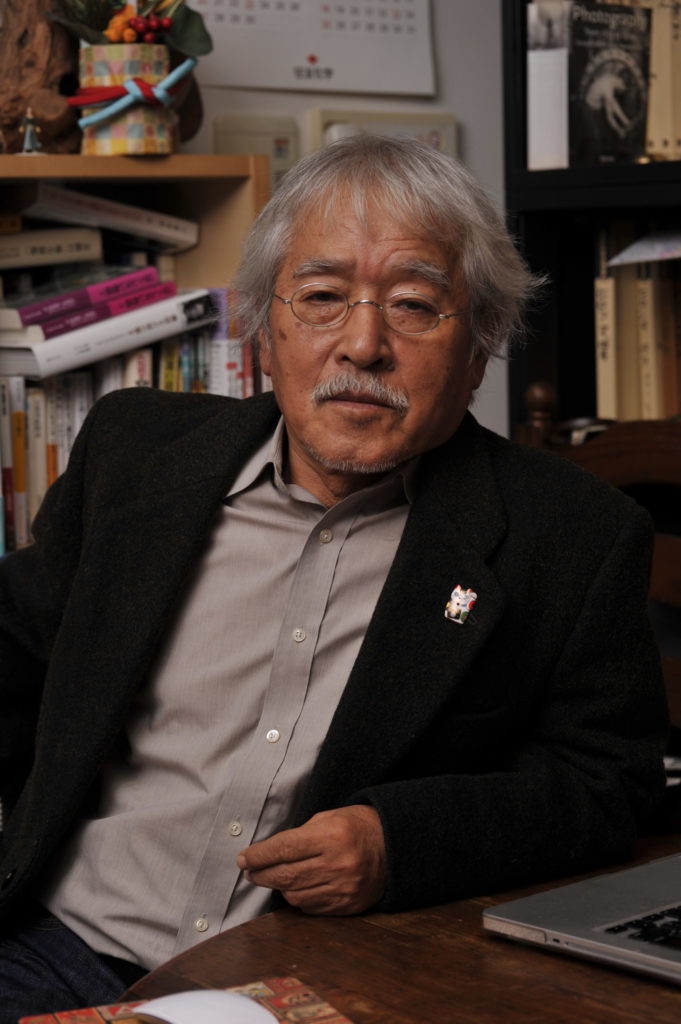日本の写真にフォーカス
デジタル出版物
このサイトは、戦後から現在に至るまで、サンフランシスコ近代美術館所蔵の膨大で多様な日本の写真コレクションを中心に、過去60年間の主要な写真家の仕事を通じて、日本の独特で革新的な写真文化の発展を検証しています。 戦後日本における連合軍の占領とベトナム戦争期における在日米軍の拡大、1980年代の目覚ましい経済成長とその後に起きたバブル崩壊、そして2011年に東北地方で起きた東日本大震災までの激動の時代でありながらも芸術的に肥沃な時代を、写真家たちの経歴、講演会の内容、ビデオインタビューやその他の資料で洞察します。

NIKONは100年以上にわたり、私たちの日常生活を改善し、より美しい芸術を創造し、人類の最大の課題のいくつかを解決するために、新しく革新的な画像技術を追求してきました。これらの影響力のある写真家の重要な作品やストーリーを世界に届けるサンフランシスコ近代美術館の『日本の写真にフォーカス』に協力できることを誇りに思います。